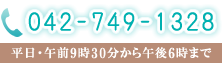様々な紛争・手続
契約履行トラブル
市民生活は、商品売買、工事請負、サービス提供契約といった契約で成り立っています。お金の貸し借りも金銭消費貸借契約という契約です。これら契約で生じるトラブルは、「頼んだことをやってくれない」「期待したものと違う」「ちゃんとお金を支払ってくれない」といったものです。その原因には「信頼して契約の内容を確認しなかった」「後から事情が変わった」といったものがあります。何かの企てがある場合もあります。困っている一方の不安が高まってきたところに、もう一方が突き放すような対応をして、争いが激化することが少なくありません。
不満があれば、契約の相手方に対して「決めたとおりにちゃんとやって欲しい」「契約をなかったことにして欲しい」「損害賠償を支払って欲しい」といった請求をします。これらの請求を交渉や民事訴訟などを通じて解決します。
交通事故
交通事故は、突然発生する危険な事故ですから、大変ショックな出来事です。ほとんどの原因は過失ですが、危険運転が原因で事故が起きるケースもあります。
交通事故では、基本的に、当事者が自動車損害賠償責任保険(自賠責)や任意保険に加入しています。通常、これら保険から一定の保険金が支払われます。問題は適正な賠償金額が支払われるかどうかです。
なお、事故直後の当事者のふるまい、ことばを気にされる方も多いですが、解決に影響ない場合も多いです。
不満があれば、事故の相手方に対して、損害賠償請求を求めます。交渉や訴訟などを通じて解決します。
ご注意いただきたいのは、任意保険に加入している場合、弁護士費用特約によって弁護士費用を負担しなくてよい場合があることです。保険会社からの申し出を待たずに必ずご自身で任意保険に問い合わせしてください。
不動産賃貸
不動産賃貸は、賃貸借契約の一種です。借りる人(賃借人)は生活の本拠として借りる場合もありますし、店舗として借りる場合もあります。争いは、契約当初には考えていなかった事情から生じることが多いです。賃借人は、突然契約を解消されると困ってしまうため、オーナーに対して自己主張しづらい場合があります。そこで法律は、賃貸借契約書の内容にかかわらず、賃借人の立場を強化しており、近年ではこの法律の趣旨も社会に浸透してきています。法律の規定と時代の変化から、オーナーの認識と賃借人の主張に食い違いが生じることがあり、争いに発展することがあります。
不満があるオーナーは「ちゃんと家賃を支払ってほしい」「毎月の家賃を増額して欲しい」「出て行って欲しい」といった請求をします。不満がある賃借人は「毎月の家賃を下げて欲しい」「修繕して欲しい」といった請求をします。賃借人が建物を退去した後の段階では、オーナーからは「原状回復費用を払って欲しい」、賃借人からは「敷金を返して欲しい」といった求めがあることもあります。これらの請求を、訴訟、調停などを通じて解決します。
労働契約
労働契約も契約の一つです。社員、パート、アルバイトは生活のために働きます。労働者は会社に遠慮をして、会社に対して自己主張しづらい場合があります。そこで法律は、労働契約や就業規則の内容にかかわらず、労働者の立場を強化しています。労働者の権利と会社の指揮命令権には複雑な緊張関係にあります。
争いは、会社の方針変更や労災事故があって生じることもありますし、労働者が退職した際、たまっていた労働者の不満が噴出して始まることもあります。会社在籍中に裁判などになることは少ないのが現状です。いずれにしても誤解による行き違いがないように会社と労働者の日頃からのコミュニケーションが重要です。
なお、労働災害の場合、交通事故の自賠責と同様、労災保険から保険金が払われますが、十分な金額とは限りません。
不満がある労働者は「不当に安い賃金を適性な額にして欲しい」「そのような解雇は許されない」「そのような業務命令は許されない」「十分な損害賠償を支払って欲しい」といった請求をします。これらの請求を交渉、労働審判、訴訟、労働委員会での手続などで解決します。労働組合が関与する解決手段もあります。
会社側は、基本的に受身的立場で対応することになりますが、個人と相対する組織として、紳士的な姿勢が期待されます。
離婚
離婚の場面では、一緒になった二人が、どうしても別れたいという気持ちになっています。「顔も見たくない」という気持ちになっていることも少なくありません。それでも、夫婦、子供たちにはそれぞれ未来があります。冷静に夫婦関係・親子関係を検証し、前向きに将来の人生設計をたてなければなりません。
離婚問題の特徴は、夫婦間のやりとりは日々無数にあること、夫婦間には第三者が外から評価しづらい、高度にプライベートな事情があることです。そのため、裁判所が逐一踏み込んだ判断をしづらい側面があります。
相手に不満がある側は「離婚したい」「相手名義になっている財産を自分に分けて欲しい(財産分与)」「慰謝料を払って欲しい」「生活費や養育費を払って欲しい」「自分も年金を受け取れるようにして欲しい」といったことを請求します。
請求の中で大きなウェイトを占めることが多いのは、財産分与です。これは婚姻期間中に築いた財産を二人でわけるものです。婚姻期間が長期にわたる場合には、大きな金額が争われることが多く、離婚自体を合意する交渉の条件としても重要です。
これらの請求を交渉、調停、訴訟で解決します。離婚訴訟は調停をしても解決しなかった場合でなければできません。
相続
相続では、亡くされたご家族(被相続人)の財産をどのように分けるかを決めます。親と一緒に暮らしていて介護に従事していた方と、家を出て親から自立して生計を立てていた方の中で不仲になる場合があります。また、被相続人の生前、相続人の一人が相続対策をしていたことが明らかになって信頼関係が崩れ、争いのきっかけになることもあります。
不満がある相続人は、遺産分割協議で「ちゃんと遺産を教えて欲しい」「介護していたことを評価して欲しい」「相手だけお金をもらっていたことを評価して欲しい」「自分はこの遺産を欲しい」といったことを請求します。これらを遺産分割協議、調停で解決します。遺言がある場合でも、不満があれば「遺言は無効」「遺言は遺留分を侵害しているから侵害している金額を払って欲しい」といったことを請求します。これらの請求を交渉、調停、訴訟で解決します。
なお、「相続に関わりたくない」あるいは「被相続人には債務しかない」という場合には、相続放棄という制度が用意されています。
多重債務
事業や生活のために借り入れをしたものの、どうしても、計画どおりに返済をすることができなくなる場合があります。多重債務に苦しむ方の多くは、長い間、厳しい取り立てや資金の工面に追われ、精神的な健康を害してしまいます。生活再建が急務です。将来のあてのない、その場しのぎの対応ではなく、勇気をもって根本的な解決をしなければなりません。
①債権者と交渉で解決する任意整理、②裁判所に申し立てて、住宅ローン以外の債務を約5分の1にして自宅の所有権を確保する民事再生、③財産をほとんど手放すかわりに法的な債務をなくす自己破産があります。特に自己破産を選択した方の多くは「もっと早く自己破産を決断して、早く一からやり直せばよかった」と口にされます。
後見
年齢を重ねることはすばらしいことですが、認知能力が低下することもあります。判断能力が低下すると、その方(本人)が間違って財産を使ってしまうかもしれません。誰かが財産を持っていってしまうこともあります。法律上は判断能力がない人の契約を無効にしていますが、裁判で裁判所がどのように判断するかは、事前には分かりません。
そこで法律は、トラブルが起きる前に認知能力が低下した方を要保護者として認定し、その方が一人で確定的に契約を結べなくなくなるようにする制度を用意しています。それが法定後見制度(後見・保佐・補助の3タイプがあります。)です。この法定後見制度は、知的障害で判断能力がない方のためにも利用されます。
また、認知能力が低下する前に、本人が自分の保護者を決め、財産の使い方を決めておく制度もあります。こちらは任意後見制度といいます。
刑事事件
刑事事件は、いわゆる犯罪事件ですが、刑事手続は、犯罪をした人に国家が制裁を与えるかどうかを判断するための手続です(民事事件は、事情に応じて財産を再配分させるかどうかを判断するための手続です。)。一つの事件について、刑事手続と民事手続の両方の対象になることもあります。相互に影響がないとはいいきれませんが、法的には別個の手続です。
犯罪には、万引きなどの窃盗、傷害から、放火、殺人といった重大な犯罪まで様々なものがあります。覚せい剤自己使用のような薬物事件もあります。
犯罪の背景には、財産目的、怨恨、カッとなってしまったという激情、脅かされてまともな判断ができなかったといったことがあります。万引きのときの緊張感など一定の精神状態への依存があったという場合もあり、なかには病気と判断されて、裁判で考慮されるものもあります。事故では過失がとわれます。
捜査や裁判の対象になると、捜査対象者やその親族に大きな負担がかかります。
身柄が拘束されると身体の自由が奪われ、人格や社会的地位が大きく損なわれます。身柄拘束が「人権の包括的制限」といわれるゆえんです。捜査・裁判の対象になった方は国家権力と対峙することになり、また、社会的に孤立することになります。しかし、冤罪は絶対に阻止しなければなりません。また、犯罪を犯した人であっても、不当に重い刑罰が科されないようにしなければなりません。
一方で、犯罪被害者保護の声も高まっており、被害者が受けた苦痛や心情も、裁判に反映されなければなりません。
M&A
“Mergers and Acquisitions”の略で、「合併と買収」という意味です。広い意味では企業再編や企業提携も含みます。
企業の結合によって得られる相乗効果(シナジー)を活用するために、あるいは、企業の分離によって経営リスクを分散するために利用されます。
企業買収は、かつては「企業精神をお金で売り渡す」ようなネガティブな印象をもたれたことがありました。しかし、近年では合理的判断が尊重され、そのような印象は薄れつつあります。それでも、敵対的企業買収は社会の注目を集め、また、企業買収は国のアイデンティティ・競争力・国の自給能力の確保といった視点からも注目されます。
会社法上の組織再編手段として、金銭と引き換えに資産や事業体を移転する事業譲渡、事業体が移されて移転元の会社が消滅する合併、事業体が移されて元の会社が存続する企業分割や子会社設立があります。株式交換や株式交付という特殊なものもあります。いずれも企業体にとって重要な再編成ですから、事業予測や相手企業の業績・財務調査が重要です。法的には、原則として株主総会の特別決議や会社債権者らを保護する手続が求められます。